東京のすし屋の娘でもある、江戸前寿司伝道師Satomiです。
皆さんのイメージするすし職人はどんな人ですか?
・がんこ
・気難しい
・こわい
など、すし職人はちょっとこわいイメージがある人も多いのではないでしょうか。
もしも、すし屋がイケメンだったらあなたは通いますか。
今回は、江戸時代のすし売りの話をしたいと思います。
江戸期の歌
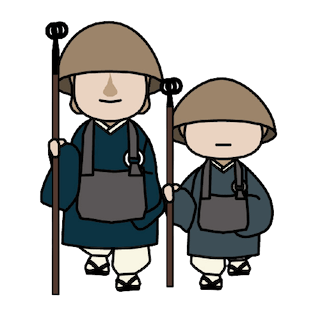

『天言筆記』(1846年)にこんな歌があります。
「坊主だまして還俗させて、いなりのすしでも売らせたや」
墜落した僧侶を稲荷信仰でよみがえらせればいいという、宗教をからかう意図があると言われています。
江戸時代の稲荷寿司

当時の稲荷寿司は海苔巻きなどのように細長く、一本16文、半分8文、一切れ4ぶんと切り売りされていました。
細長い稲荷寿司は、埼玉県熊谷市妻沼の郷土料理として現存しています。
替え歌


江戸期の歌で、『天言筆記』(1846年)を替え歌した歌があります。
「坊主だまして還俗させて、こはだのすしなど売らせたや」
という歌です。
昔の坊主は美男が多かったので、寿司を売らせてみたいということだそうです。
Youtube
まとめ
「ジャニーズ系」という言葉がありますが、昔の坊主はジャニーズ系だったというイメージでしょうか。
好みはそれぞれあると思いますが、ジャニーズ系のすし屋がいたら、毎日売れすぎて大変だったかもしれませんね。
まさに、スシ王子!
ラインで友達登録していただけると、友達限定情報などを送っております♬
すし文化を学び、自分なりのすしの楽しみ方を実践していただく「寿司屋の娘と楽しむカウンター寿司」のすし付き講座はいかがですか?
江戸前寿司を気軽に楽しめるようになりたい方は「寿司道」がお薦め。
カッコよくエスコートできるようになりたい方は「プリン酢コース」をお薦め。
ライバルに差をつけたい方は「玉本芸人コース」がお薦め。
握り寿司、巻き寿司、ちらし寿司、刺身に詳しくなり、より楽しめるようになりたい方は「ガリウッドコース」がお薦めです。
各コース、リンク先から、ご予約いただけます。
カルチャーセンター、大学、企業研修等の出張講座も承ります。お気軽にご相談ください。
皆様にお会いできることを楽しみにしております♬

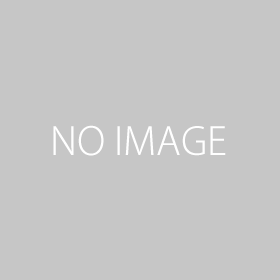
この記事へのコメントはありません。