東京のすし屋の娘でもある、江戸前寿司伝道師Satomiです。
皆さんは、麹を使った料理を選んで食べますか。
麹は寿司を作る上でとても重要なものです。
今回は、寿司と麹の関係をお話ししたいと思います。
麹とは
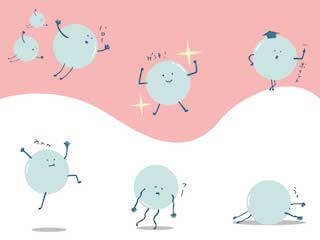
「麹」は麹菌というカビの一種を使用した発酵食品で、日本を代表するものとして選ばれた「国菌」です。長い間、日本の食文化に深く根付き、豊かな日本食の醸成に貢献してきました。
「麹」と「糀」
「麹」と「糀」という、異なった表記を見かけるのではないでしょうか。
どう違うのか考えたことはありますか。
「麹」と「糀」の違いは漢字の違いだけで、あらわしているものはどちらも同じです。
「麹」
中国からきた漢字
「糀」
日本で作られた国字
「米にコウジカビが生える様子が、花が咲くように見える」ことから、生まれた漢字。
3種類の麹
麹とは、米、麦、豆などの原料となる穀物を蒸したものに「麹菌」を付着させ、繁殖しやすい温度、湿度などの条件下で培養したものです。
麹には原料ごとに異なる3つの種類があります。
①米麹
日本で、最もよく知られていて、よく使われているのが「米麹」です。
原料となるお米に麹菌を生やし、発酵させることでつくられます。
米味噌、日本酒、みりん、酢、甘酒の原料となります。
②「麦麹」
麦を原料にしてつくられ、麦味噌や麦焼酎をつくる際に使われています。
③「豆麹」
大豆を原料にしてつくられ、豆味噌や八丁味噌などの豆味噌の原料となります。
5種類の麹菌

原料によって種類が異なる麹ですが、麹菌の種類によっても5つの種類に分けられます。
黄麹菌
麹菌の中でも緑がかった黄色をしている(黄褐色)麹菌で、主に「味噌」「醤油」「清酒」の製造に用いられます。
白麹菌
主に「焼酎」の製造に用いられます。
黒麹菌
主に「泡盛」の製造に用いられます。
紅麹菌
「豆腐よう」「紅酒」「老酒」の製造に用いられます。鮮やかな紅色をした麹をつくります。
カツオブシ菌
鰹節の製造に用いられます。
鰹節内部に残った水分の吸収や、旨味成分の生成、油脂成分の分解効果を持ちます。
健康とすしと麹



麹はバクテリアの増殖を防ぎ、ビタミンB群が多く含まれ、美肌を作り、疲労を回復させ、ダイエットにも効果的。おまけに腸を元気にしてくれるので、便秘にも良いと言われています。この麹を使って酒、みりん、酢、醤油、味噌などが作られています。
すしを作る時も、食べる時も欠かせない調味料です。
Youtube
まとめ
健康にも良い麹。日本の寿司文化は調味料なしでは語れない様ですね。
ラインで友達登録していただけると、友達限定情報などを送っております♬
すし文化を学び、自分なりのすしの楽しみ方を実践していただく「寿司屋の娘と楽しむカウンター寿司」のすし付き講座はいかがですか?
江戸前寿司を気軽に楽しめるようになりたい方は「寿司道」がお薦め。
カッコよくエスコートできるようになりたい方は「プリン酢コース」をお薦め。
ライバルに差をつけたい方は「玉本芸人コース」がお薦め。
握り寿司、巻き寿司、ちらし寿司、刺身に詳しくなり、より楽しめるようになりたい方は「ガリウッドコース」がお薦めです。
各コース、リンク先から、ご予約いただけます。
カルチャーセンター、大学、企業研修等の出張講座も承ります。お気軽にご相談ください。
皆様にお会いできることを楽しみにしております♬

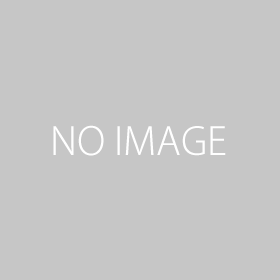
この記事へのコメントはありません。