東京のすし屋の娘でもある、江戸前寿司伝道師Satomiです。
皆さんは、「雑魚」という言葉をご存知ですか。ゲームなどをする時、「雑魚キャラ」と言っているのも聞いた事があるかもしれません。今回は「なぜ雑魚というのか」についてのお話です。
雑魚とは
自分よりも弱いものに対して、蔑む(さげすむ)ような使い方が多いのではないでしょうか。
雑魚キャラとは
ゲーム等に登場する、弱く、取るに足らず、数の多い敵キャラのことを雑魚キャラと言います。 一番最初に対峙する場合が多いキャラクターかもしれません。
「雑魚」は漁師の言葉?
もともとは漁師や鮮魚を扱う商人の間で使われていた言葉だったと言われています。
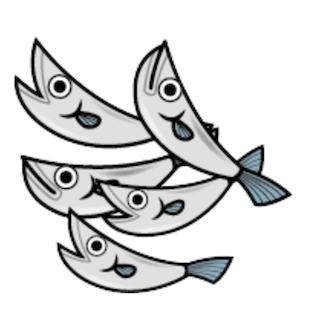
「雑魚」とは、「釣りや漁業の際に釣れる小さくて価値が薄い魚」を総称した呼び名で、漁を行った際、大きな網を使います。その中に、小さな魚もたくさん入っていて、特に小さく、種類ごとに分けることもできない商品価値の低い魚をまとめて「雑魚」と呼びます。
雑魚の語源
「雑な魚」と書いて「ざこ」と読みます。しかし、「魚」という漢字は本来『こ』とは読みません。では、なぜ『こ』と読むようになったのか…
「雑魚」は元々、「雑喉」と書き、「ざこ」ではなく、「ざっこう」と呼ばれていました。最近ではほとんど聞くことはないかもしれません。
昔は「雑喉場(ざこば)」と呼ばれる、小魚などを専門に扱う市場がありました。
「小さい魚」→「雑喉」→「ざっこう」→「ざこ」と変化し、『こ』という部分には本来の意味である「魚」が使われるようになったと言われている「当て字」です。
Youtube
まとめ
「雑魚キャラ」などと言われる「雑魚」が元々漁師の言葉だったと知らずに使う事が多いのではないでしょうか。
ラインで友達登録していただけると、友達限定情報などを送っております♬
すし文化を学び、自分なりのすしの楽しみ方を実践していただく「寿司屋の娘と楽しむカウンター寿司」のすし付き講座はいかがですか?
江戸前寿司を気軽に楽しめるようになりたい方は「寿司道」がお薦め。
カッコよくエスコートできるようになりたい方は「プリン酢コース」をお薦め。
ライバルに差をつけたい方は「玉本芸人コース」がお薦め。
握り寿司、巻き寿司、ちらし寿司、刺身に詳しくなり、より楽しめるようになりたい方は「ガリウッドコース」がお薦めです。
各コース、リンク先から、ご予約いただけます。
カルチャーセンター、大学、企業研修等の出張講座も承ります。お気軽にご相談ください。
皆様にお会いできることを楽しみにしております♬

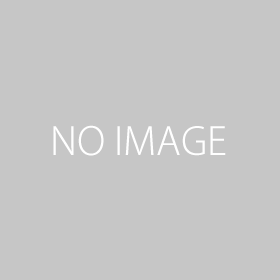
この記事へのコメントはありません。